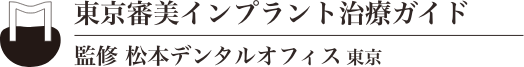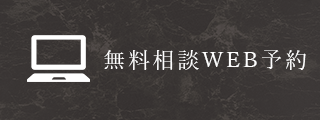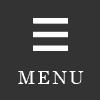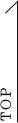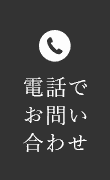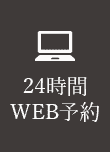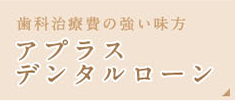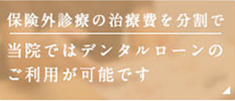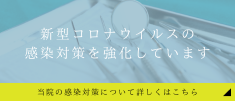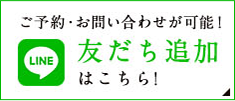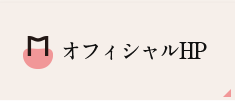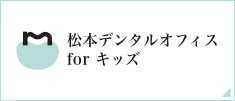こんにちは。松本デンタルオフィス東京です。
実は近年、「噛む力」が脳の働きを活性化するという研究結果が多く発表されています。歯を失い、しっかり噛めなくなると、脳への刺激が減り、認知機能の低下や認知症リスクが高まる可能性があるのです。
そこで注目されているのが、天然歯に近い噛み心地を再現できる「インプラント治療」。しっかり噛める状態を取り戻すことで、脳の健康や食生活の改善、生活の質(QOL)の向上にもつながります。
今回は、認知症と噛む力の関係、インプラントが果たす役割、入れ歯との違い、治療の安全性やメリットまで、解説していきます。
これからの人生を、もっと元気に、自分らしく過ごすために。
インプラントを通じて、「噛む力を取り戻すこと」は、未来の健康への第一歩になるかもしれません。
1.こんなお悩みありませんか?
 ・「最近、ちょっとした物忘れが増えた気がする…」
・「最近、ちょっとした物忘れが増えた気がする…」
・「食事のときにうまく噛めなくて、やわらかい物ばかり選んでしまう」
・「家族に認知症の人がいるので、自分も将来が不安で…」
特にご年齢を重ねるにつれて、「記憶力」や「噛む力」について気になってくる方が増えています。
実は、お口の健康と脳の健康は密接に関わっているということをご存じでしょうか?
「噛む」という行動には、食事を楽しむだけでなく、脳への刺激を与えて活性化させるという、とても大切な役割があります。
つまり――
しっかり噛める状態を保つことは、認知症の予防にもつながる可能性があるということなんです。
ところが、歯を失ったまま放置していたり、入れ歯が合わずに噛みにくい状態が続いていると、自然と噛む回数や力が減ってしまいます。
その結果、「食事が偏る」「外出が減る」「会話も減る」といった生活習慣の変化が起こり、脳の刺激が不足してしまうこともあるんです。
そこで近年、注目されているのが「インプラント治療による噛む力の回復」。
インプラントは、見た目が自然なだけでなく、自分の歯のようにしっかり噛めるという点が大きな特長です。
その噛む力が、食事の楽しみや栄養状態の改善はもちろん、認知症の予防にも良い影響を与えると考えられています。
「インプラントって、見た目のための治療じゃないの?」と思われがちですが、実はそれだけではありません。
インプラントは“噛む機能”を回復する医療であり、その効果はお口の中にとどまらず、全身の健康維持や予防医療にもつながる治療法なんです。
2.認知症とは?そのリスクと影響
 認知症とはどんな状態なのか、そして私たちの日常生活にどんな影響があるのか、しっかり知っておくことが予防の第一歩です。
認知症とはどんな状態なのか、そして私たちの日常生活にどんな影響があるのか、しっかり知っておくことが予防の第一歩です。
認知症の主な原因と症状
認知症とは、加齢などが原因で脳の働きが少しずつ低下し、記憶力や判断力、日常生活の機能に支障が出てくる状態をいいます。
ただの「物忘れ」とは違い、徐々に進行していくのが特徴です。
✅主な原因には以下のようなものがあります:
- ・アルツハイマー型認知症(最も多いタイプ/脳の神経細胞が減っていく)
- ・脳血管性認知症(脳梗塞や脳出血などによるダメージ)
- ・レビー小体型認知症(幻視や運動障害などが出やすい)
- ・前頭側頭型認知症(人格や行動に変化が現れるタイプ)
症状としては、以下のようなことが起きやすくなります:
- ✔同じ話を何度も繰り返す
- ✔約束を忘れる、物の置き場所が分からなくなる
- ✔簡単な計算や段取りが難しくなる
- ✔感情が不安定になったり、意欲が低下する
認知症が日常生活に与える影響
認知症は、初期のうちはご本人も「ちょっとおかしいかな?」と感じる程度かもしれません。
しかし、徐々に日常生活にさまざまな影響が出てきます。
✅日常生活への影響例
- ・食事の準備や買い物が難しくなる
- ・薬の飲み忘れが多くなる
- ・道に迷いやすくなる、外出を避けるようになる
- ・家族との会話がかみ合わず、孤立感を感じる
また、ご本人だけでなく、周囲のご家族にも大きな負担がかかるようになります。
介護やサポートが必要になる場面が増えるため、早めの予防・対策がとても大切なんです。
認知症予防のためにできること
「もう年だからしょうがない」と思ってしまう方もいらっしゃいますが、認知症は予防や進行の遅延が可能です。
✅認知症を予防するために意識したいこと:
- ・バランスの良い食事(脳に良い栄養をしっかりとる)
- ・よく噛んで食べる習慣を持つ(噛むことで脳が刺激され活性化)
- ・適度な運動や外出、会話の機会を増やす
- ・趣味や交流を続ける(社会とのつながりが脳を元気にします)
- ・高血圧や糖尿病などの生活習慣病をしっかり管理する
この中でも特に注目されているのが、「噛むこと」と「口腔機能の維持」です。
噛む力が衰えると、食事が偏ったり、外食や人との会話を避けるようになるなど、生活の質が下がりがちです。
逆に、しっかり噛める状態を保つことは、脳の血流を良くし、神経を刺激して認知機能の低下を防ぐ可能性があると言われています。
歯を失ってしまった場合でも、インプラントなどで噛む機能を回復することで、しっかりとした食生活と脳の活性化が期待できます。
入れ歯が合わずに噛めないままでいると、知らず知らずのうちに「噛む力」が失われてしまい、結果として認知症のリスクを高めてしまうこともあります。
3.噛む力と脳の健康の関係
 「しっかり噛んで食べることが、脳にいいらしいよ」
「しっかり噛んで食べることが、脳にいいらしいよ」
そんな話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
実はこの「噛む」という行動、私たちが思っている以上に脳にとって重要な役割を果たしているんです。
最近の研究では、「噛む力」が認知症予防に関係していることが、科学的にも少しずつ明らかになってきました。
「噛むこと」が脳に与える刺激とは?
食べ物をしっかり噛むとき、あごの筋肉が動くだけでなく、脳にも強い刺激が送られています。
特に刺激を受けているのは「海馬(かいば)」と呼ばれる記憶をつかさどる部分や、前頭葉などの「判断・思考」を担当する部分です。
この刺激によって、脳内の血流が良くなり、神経細胞の働きが活性化されると言われています。
つまり、噛むことで“脳のスイッチ”が入るようなイメージです。
子どもの発達においても「よく噛むこと」が脳の発育に良い影響を与えることが知られていますが、
これは大人や高齢の方にとっても同じことが言えるんです。
噛む回数が減ると脳にどんな影響がある?
では逆に、歯を失ったり入れ歯が合わなかったりして、噛む回数が減ってしまったらどうなるのでしょうか?
✅噛む機能が低下すると――
- ・食べ物をしっかり咀嚼できず、栄養が偏る
- ・噛む刺激が脳に届かず、脳の働きが弱まる
- ・外食や人との会話が減り、社会との関わりが薄れる
このように、身体的・精神的な影響がじわじわと現れてくることがあります。
中でも「脳への刺激の減少」は見過ごされがちですが、認知機能の低下と密接に関わっているんです。
研究でわかった「咀嚼」と認知機能の関係
最近では、噛む力と認知症の発症リスクに関する研究も多数行われており、以下のようなことが分かってきています。
✅代表的な研究内容:
- ・歯の本数が少ない人ほど、認知症のリスクが高まるという報告(日本の疫学調査より)
- ・奥歯でしっかり噛める人は、脳の海馬の萎縮が少ないというデータ
- ・咀嚼機能が高い人は、脳血流が豊富で認知機能も高い傾向があるとするMRI研究も存在します
こうしたデータからも、「よく噛めること」は単なる食生活の質を上げるだけでなく、脳の健康維持に直結していると考えられます。
インプラントで「噛む力」を取り戻す意義
噛む力が衰えたと感じたとき、早めにその機能を回復することが大切です。
中でも、インプラント治療は失った歯をしっかりと固定し、天然歯のように噛めるようになるため、咀嚼力の回復にとても優れた選択肢です。
入れ歯ではうまく噛めなかったという患者様も、インプラントにして「以前のように何でも食べられるようになった」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
また、インプラントによってしっかり噛めるようになると、食事が楽しくなり、外出や会話も自然と増え、生活の質そのものが高まります。
その結果、脳への刺激が増え、認知症予防にもつながるという好循環が生まれやすくなるのです。
噛むことは、毎日の食事や会話の中にある自然な行動ですが、実は“脳を元気に保つ鍵”でもあるのです。
4.歯の喪失と認知症リスクの関係
 「歯を失うと、見た目や食事が不便になるだけじゃないの?」
「歯を失うと、見た目や食事が不便になるだけじゃないの?」
そう思われるかもしれません。たしかに、歯がなくなることで見た目が変わったり、噛みにくさを感じたりするのはよく知られています。
ですが実は、歯の喪失は「脳の機能」とも深く関わっているんです。
特に近年では、歯の本数と認知症のリスクには明確な関係があることが、研究で次々と明らかになってきています。
歯を失うことが脳の機能低下につながる理由
まず、私たちが食事をするとき、「噛む」という動きによって脳が刺激を受けて活性化されるというお話を、前の章でもご紹介しました。
そのため、噛むための歯が減ってしまうと、自然と噛む回数や噛む力が落ち、脳への刺激も減ってしまうのです。
特に、奥歯など「しっかりと噛むために重要な歯」を失ってしまうと、噛む機能そのものが大きく低下します。
✅また、歯を失うことは――
- ・食事の満足感の低下(よく噛めない、味がわかりにくくなる)
- ・噛む力の左右バランスの崩れ(片側だけで噛む癖がつく)
- ・食事が偏りやすくなり、栄養不足につながる
- ・外食や会話の機会が減る
こうした生活の変化が積み重なって、脳の働きにも悪影響を与えてしまうことがあるのです。
研究が示す「歯の本数」と認知症リスク
日本国内外のさまざまな研究で、「歯の本数」と「認知症の発症率」には明確な関係があることが報告されています。
たとえば――
- ・自分の歯が20本以上ある人に比べて、歯が10本未満の人は認知症のリスクが約2倍になるという報告
- ・奥歯を失って噛む力が大きく落ちた人は、脳の記憶をつかさどる「海馬」が萎縮している傾向があるとするMRI画像研究
- ・咀嚼機能が高い人ほど、脳の血流が多く、認知機能テストの成績も良いといったデータもあります
つまり、「歯が少なくなる=ただの老化現象」ではなく、脳にも影響を与える重大な健康リスクと考えるべきなのです。
入れ歯では補えない機能とは?
「じゃあ入れ歯があるから大丈夫」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、入れ歯は見た目を整えたり、ある程度の咀嚼機能をサポートしたりするのに役立ちます。
ただ、入れ歯では天然の歯やインプラントと比べて、噛む力や脳への刺激が大きく劣ることがわかっています。
✅入れ歯では補いきれない部分の一例:
- ・噛む力が弱く、しっかり咀嚼できない
- ・硬いものや弾力のある食べ物を避ける傾向が強くなる
- ・会話中に外れやすく、不快感がある
- ・脳に伝わる刺激(噛む・圧を感じる信号)が少ない
その結果、「噛んでいるつもり」でも脳があまり反応しておらず、十分な活性化につながらないケースが多いのです。
インプラントで「しっかり噛める」生活を取り戻す
そこで注目されているのが、インプラント治療です。
インプラントは顎の骨にしっかりと固定されているため、まるで自分の歯のようにしっかり噛めるのが特長です。
硬いもの、繊維質のある食材、好きな食べ物をしっかり噛んで味わえることが、脳への刺激や認知機能の維持にとても効果的と考えられています。
また、違和感が少なく、外れる心配もないため、会話や笑顔にも自信が持てるようになり、結果として「外出が増える」「人と話す機会が増える」など、生活全体の活性化にもつながります。
「歯を失ったから仕方ない」とあきらめず、これからの人生を元気に過ごすために、“噛む力”を取り戻すことが大切です。
5.インプラント治療が認知症予防に有効な理由
 これまでのお話の中で、「噛むことが脳に刺激を与える」「歯を失うことが認知症のリスクにつながる」ということをご紹介してきました。
これまでのお話の中で、「噛むことが脳に刺激を与える」「歯を失うことが認知症のリスクにつながる」ということをご紹介してきました。
では、失った歯を補う方法の中で、なぜインプラントが特に注目されているのでしょうか?
インプラントで回復する「噛む力」
インプラントは、顎の骨に人工の歯根(インプラント体)をしっかりと固定し、その上に人工の歯を装着する治療法です。
これにより、「グッと力を入れて噛む」ことができるようになるのが最大の特長です。
入れ歯と比べても――
- ・動かない
- ・外れない
- ・噛む力が強く、左右バランスも整う
つまり、天然の歯に近いレベルで「噛む」という動作が回復するのです。
この「しっかり噛める状態」が、脳への良い刺激を再び送り始めることにつながり、
その結果として、認知機能の維持や低下の予防に役立つ可能性があると言われています。
天然歯と変わらない噛み心地のメリット
入れ歯は見た目が整っても、「噛みにくい」「外れやすい」「硬い物が食べられない」といった不満を感じている患者様が多いのが現実です。
その点、インプラントは――
✅ 天然歯に近い噛み心地を得られることで、
- ・「よく噛める」ことで食事の満足感が大きくなる
- ・「味がわかりやすくなる」ため、食欲が戻る
- ・「外出して人と一緒に食事を楽しむ機会」が増える
- ・「会話のストレスが減る」ことで社会との関わりも自然に増える
このように、生活の質そのものを高める効果があり、それが脳の活性化や精神面の安定にもつながっていきます。
認知症予防におけるインプラントの役割
近年の研究では、インプラントで咀嚼機能を回復した患者様の方が、認知機能の低下が起こりにくい傾向があることも示されています。
さらに、噛む力が戻ることで――
- ・脳の記憶をつかさどる海馬の萎縮が抑えられる可能性
- ・脳の血流量が増え、思考力や集中力の維持に効果
- ・食事・会話・社会的活動の増加により、うつ症状の予防や改善にも貢献
このように、インプラントは「歯を補うための治療」であると同時に、「脳と心を元気に保つ治療」でもあると言えるのではないでしょうか。
「噛めること」は、あたりまえのようで、実は心と体の健康を支える“土台”なんです。「歯がないのは年だから仕方ない」ではなく、これからの10年、20年を快適に生きるために、今できるケアをはじめてみませんか?
6.インプラントと入れ歯の違いを比較
 「歯を失ったとき、入れ歯にするかインプラントにするか迷っている」
「歯を失ったとき、入れ歯にするかインプラントにするか迷っている」
「認知症予防にいいのはどっちなの?」
たしかにどちらも、失った歯を補うための治療方法ですが、噛む力や安定性、脳への刺激の強さには大きな違いがあります。
噛む力・安定性・脳への刺激の違い
【入れ歯の場合】
- ・歯ぐきの上にのせて使うタイプのため、噛む力は自分の歯の2~3割程度
- ・外れたり、ズレたりしやすく、食事中や会話中に違和感を感じることがある
- ・噛んでいる“つもり”でも、顎の骨や神経を通して脳へ伝わる刺激が弱い
【インプラントの場合】
- ・顎の骨にしっかりと固定されているため、噛む力は天然歯とほぼ同等
- ・グラつきや違和感がなく、硬いものや繊維質の食材も自然に噛める
- ・噛む刺激がしっかりと脳に届くため、脳の活性化が期待できる
このように、「しっかり噛む力」が戻るという点では、インプラントの方が圧倒的に有利です。
特に、脳への刺激という面では、“どれだけ噛めているか”がそのまま影響すると考えられています。
インプラントが認知症予防に適している理由
「噛むことで脳に刺激が伝わる」という仕組みは、すでに多くの研究でも証明されています。
そして、噛む力が強いほど、脳の血流が良くなり、記憶や判断をつかさどる“海馬”の萎縮を防ぐ効果があるといわれています。
インプラントはその「噛む力」をしっかり回復できるため、認知症のリスクを下げる可能性がある治療としても注目されています。
✅噛めるようになると――
- ・食事の内容が豊かになり、栄養状態が改善
- ・食事が楽しくなり、外出や人との交流も増える
- ・日々の生活にメリハリが生まれ、脳の活性化につながる
このように、「噛めるようになること」が、生活全体を元気にしてくれる好循環につながります。
入れ歯とインプラントの選び方
もちろん、すべての患者様にとってインプラントが最適というわけではありません。
それぞれの治療にはメリット・デメリットがありますので、以下の点を参考に、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
【入れ歯が向いている方】
- ・手術を避けたい方
- ・ご年齢や健康状態により外科処置が難しい方
- ・短期間で歯を補いたい方
【インプラントが向いている方】
- ・自分の歯のようにしっかり噛みたい方
- ・硬いものや好きな食べ物を楽しみたい方
- ・将来の健康や認知症予防を見据えている方
- ・噛む力をしっかり取り戻して生活の質を高めたい方
迷ったときは、「どちらがより噛めるか?」「自分の健康にとってどちらがプラスになるか?」という視点で比べてみるとよいでしょう。
「歯を補うための治療」ではなく、「未来の健康を守るための選択」として、ぜひインプラントという選択肢も知っておいていただけたらと思います。
7.高齢者がインプラント治療を受けるメリット
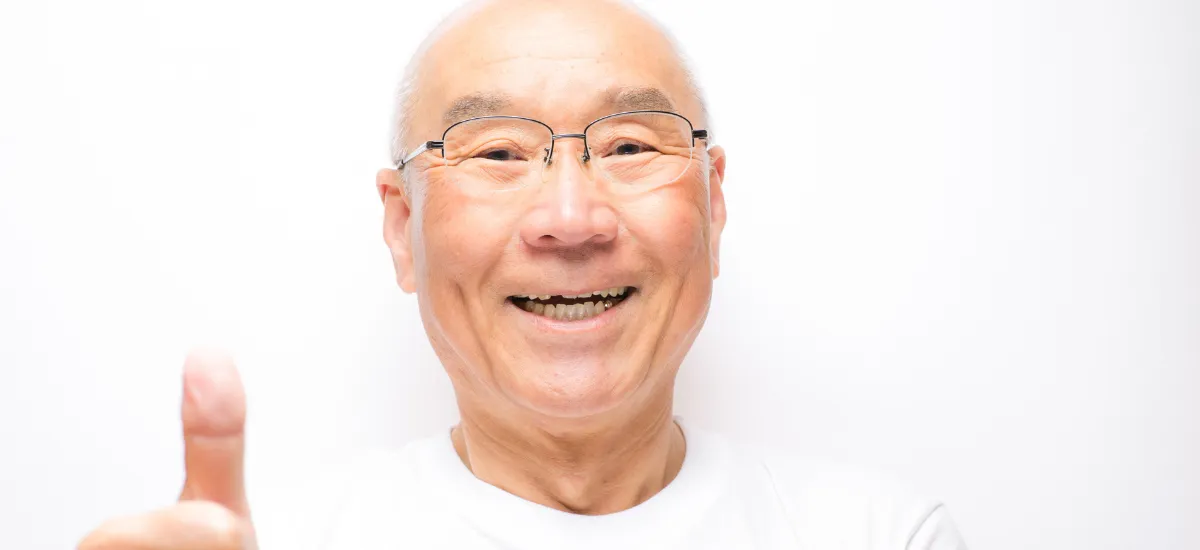 「もう歳だからインプラントは無理かな…」
「もう歳だからインプラントは無理かな…」
「高齢になると手術は避けたほうがいいのでは?」
こんなふうに思って、インプラント治療を諦めている方も少なくありません。ですが、実は高齢の患者様こそ、インプラント治療で得られるメリットがとても大きいんです。
誤嚥性肺炎の予防につながる
高齢者にとって、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)は非常に注意すべき病気です。
これは、食べ物や唾液が誤って気管に入ってしまい、肺に炎症を起こすもので、高齢者の肺炎の多くがこれに該当すると言われています。
では、なぜインプラントが誤嚥を防ぐことにつながるのでしょうか?
それは、インプラントによって「しっかり噛む」機能が回復することで、食べ物が適切な大きさ・やわらかさに咀嚼され、飲み込みやすくなるからです。
加えて、噛む回数が増えることで唾液の分泌も促され、飲み込みを助ける力もアップ。
さらに、舌や口の筋肉の働きも活性化されるため、結果的に誤嚥のリスクが減ってくるのです。
栄養バランスの向上で全身の健康を支える
「入れ歯が合わなくて、やわらかい物ばかり食べている」
「噛むのがつらくて、食事の量が減ってきた」
こうしたお悩みは、年齢を重ねた患者様からよくお聞きします。
しかし、噛めない状態が続くと、栄養が偏り、筋力や免疫力の低下につながることも少なくありません。
インプラントでしっかり噛めるようになると、肉や野菜など繊維質のある食材も自然に取り入れられるようになり、食事の選択肢が広がります。
✅噛めることで得られる栄養的メリット:
- ・たんぱく質がしっかり摂れることで、筋力維持に役立つ
- ・ビタミン・ミネラルが補給でき、免疫力を高めやすくなる
- ・バランスのよい食事で、生活習慣病の予防にもつながる
このように、インプラントは“食べられる喜び”を取り戻すだけでなく、全身の健康を支えるベースにもなるんです。
見た目の若々しさを保てる
「歯が抜けたことで、口元にシワが増えた気がする」
「顔全体が老けた印象になった」
実はこれ、歯を失うことで起きる「口元のボリュームダウン」によるものなんです。
インプラントは、顎の骨に直接固定される構造のため、噛む力だけでなく、骨の吸収(やせ)も抑える効果があります。
そのため、頬や口元のハリが保たれ、見た目の若々しさをキープしやすくなるんですね。
また、しっかり噛めることで笑顔にも自信が持てるようになり、外出や人との会話も増える傾向にあります。
こうした日常の変化が、精神面にも良い影響を与え、心身ともに前向きな生活につながっていきます。
もちろん、インプラント治療は外科手術をともなうため、ご年齢や全身状態に合わせた慎重な判断が必要です。
8.高齢者でも受けられる?インプラント治療の安全性
 インプラント治療は高齢の方でも受けていただけるケースがたくさんあります。
インプラント治療は高齢の方でも受けていただけるケースがたくさんあります。
確かに手術が必要な治療ではありますが、年齢だけを理由にインプラントができないということはありません。
年齢制限はあるのか?
まずよく聞かれるのが、「何歳までインプラント治療ができるの?」というご質問です。
結論から言えば、インプラント治療に“年齢制限”はありません。
大切なのは、年齢よりも全身の健康状態。
以下のような点をチェックしながら、治療の可否を判断していきます。
✅インプラント治療前に確認するポイント
- ・高血圧や糖尿病などの持病のコントロール状態
- ・骨の状態(顎の骨の量や質)
- ・服用しているお薬との関係
- ・手術に耐えられる体力や免疫状態
これらを事前にしっかりと検査・診断することで、無理のない、安全な治療計画をご提案することができます。
骨が少なくてもできるインプラント治療
高齢の方によくあるのが「骨がやせてしまっている」ケース。
長年歯を失ったまま放置していると、噛む力がかからなくなった部分の骨が少しずつ吸収されてしまうんです。
でもご安心ください。
近年では、骨が少ない場合でも対応できるインプラント治療法がいくつも登場しています。
✅代表的な方法:
- ・骨造成(GBR):骨を補う処置を行い、インプラントを安定させる
- ・サイナスリフト/ソケットリフト:上顎に骨を増やしてインプラントを埋入
- ・短いインプラントや傾斜埋入法:骨が薄い部分にも対応できる特殊な設計
つまり、骨が少ないからといって諦める必要はなく、専門的な診断と技術があれば治療が可能な場合が多いんです。
健康状態とインプラントの適応条件
インプラント治療を安全に進めるには、全身の健康状態が大きく関係してきます。
具体的には、以下のような点が重要になります。
✅慢性疾患の有無とコントロール
- 糖尿病がある場合は、血糖値がコントロールされているかがポイント
- 高血圧や心疾患も、主治医の指示に基づいた治療計画が必要です
✅喫煙の習慣
- タバコは傷の治りを遅くし、インプラントの成功率を下げる要因になります
- 禁煙のご協力をお願いする場合もあります
✅服薬状況
- 抗血栓薬や骨粗しょう症治療薬など、治療に影響を及ぼす可能性がある薬は事前に確認が必要です
このように、患者様ごとの健康状態にあわせて治療の進め方を調整することが、インプラント成功のカギとなります。
「年齢的にもう遅いかも…」と思っていらっしゃる方も、ぜひ一度ご相談ください。
私たちは、これからの人生をもっと快適に、もっと楽しく過ごすための選択肢として、インプラント治療をご提案しています。
9.インプラント治療後のメンテナンスと長持ちさせるコツ
 インプラントは「入れたら終わり」の治療ではありません。
インプラントは「入れたら終わり」の治療ではありません。
むしろ、治療が終わってからが本当のスタートです。
インプラントは天然歯に近い見た目と噛み心地を取り戻せる素晴らしい選択肢ですが、適切なケアと定期的なメンテナンスを続けてこそ、その効果が長く保たれます。
インプラントの寿命を延ばすポイント
インプラントは人工物なので虫歯にはなりませんが、インプラントの周囲に炎症(インプラント周囲炎)が起こると、支える骨が溶けてしまうことがあります。これが進行すると、せっかく入れたインプラントが抜け落ちてしまうことも。
そこで、日常生活で気をつけてほしいのが以下のポイントです。
✅インプラントを長持ちさせるための基本ケア
- ・毎日のブラッシングを丁寧に行う(やさしく、時間をかけて)
- ・歯間ブラシやフロス、専用のインプラント用ケアグッズの使用
- ・歯科医院での定期的なメンテナンス(3〜6ヶ月に1回)
- ・噛み合わせのチェック(インプラントに過剰な負担がかかっていないか)
- ・喫煙を控える(血流が悪くなり、炎症リスクが上がるため)
特にインプラントは「見た目がきれい=清潔」とは限りません。見えない部分で汚れがたまってしまうことがあるので、プロの目と技術でのケアが欠かせないんです。
認知症になったときのメンテナンス対策
高齢になると、認知症を発症する可能性も高くなります。
そのとき、インプラントが入っている口腔環境をどう管理していくかは、ご本人だけでなく、ご家族や介護者の関わり方がとても大切になってきます。
認知症が進行すると、歯みがきを忘れてしまったり、歯科医院への通院が難しくなったりします。そうなると、インプラントの清掃状態が悪化し、周囲炎のリスクが高まることになります。
✅認知症に備えたケアの工夫
- ・早い段階から定期メンテナンスの習慣をつけておく
- ・家族が歯みがきの補助を行うようにする
- ・訪問歯科や介護施設との連携を活用する
- ・主治医と情報を共有し、ケアプランに口腔衛生を組み込む
認知症が進行しても、インプラントを清潔に保てていれば、食べる機能や生活の質を維持しやすくなります。
そのためにも、早い段階からのサポート体制づくりが大切なのです。
家族や介護者が知っておくべきこと
インプラント治療を受けた患者様が高齢になると、どうしてもご家族や介護者の協力が必要になります。
そのため、ご家族にもぜひ知っておいていただきたいのが、次の3つのポイントです。
✅家族が知っておくと安心なこと
- ・インプラントが入っている位置・本数・治療時期などの情報を把握しておく
- ・定期検診の付き添いや通院の声かけを行う
- ・異変(口臭、出血、痛みなど)があった場合は早めに歯科へ相談する
また、万が一入院や施設への入所が決まった場合も、事前に歯科医師やケアマネージャーと情報を共有しておくと、スムーズな対応が可能になります。
インプラントは、一度しっかり入れると、患者様の生活を豊かにしてくれる“第二の歯”として活躍してくれます。
だからこそ、日々のケアと周囲の理解・協力がとても大切なのです。
10.よくある質問
 ここでは、実際によく寄せられるお悩みや疑問にお答えしていきます。
ここでは、実際によく寄せられるお悩みや疑問にお答えしていきます。
気になることがある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
Q1:インプラントをすると本当に認知症リスクが下がるの?
A1.結論からお伝えすると、「インプラントが直接的に認知症を予防する薬のような働きをする」というわけではありません。
ですが、しっかり噛めるようになることで脳が刺激を受け、認知機能の維持に役立つということは、多くの研究で明らかになってきています。
✅例えば、こんなデータがあります。
- ・噛む回数が多いほど、脳の「海馬(記憶を司る部分)」の働きが活発になる
- ・歯の本数が多い人ほど、認知症の発症リスクが低いという傾向がある
- ・歯を失っても、インプラントで噛む力を取り戻すことで、脳の血流が改善されることがある
つまり、「噛める状態を維持すること」が認知症予防に大きく関わっているということなんです。
インプラントは、そのための心強い味方のひとつと言えるでしょう。
Q2:高齢でもインプラント治療は受けられますか?
A2.「もう歳だから手術は無理かも」と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、実はそんなことはありません。
インプラント治療に年齢制限はありません。
80代で治療を受けられる患者様も、当院にはたくさんいらっしゃいます。
もちろん、以下のような健康状態の確認は必要です:
- ✅高血圧や糖尿病などの持病が安定しているか
- ✅顎の骨の量がインプラントに適しているか
- ✅体力的に無理なく処置ができるか
- ✅服用中のお薬との関係(血液をサラサラにする薬など)
「高齢だから無理かも…」と感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。
Q3:インプラントのメンテナンスはどうすればいいの?
A3.インプラントを長持ちさせるためには、「メンテナンス」がとても大切です。
天然の歯と同じように、毎日の歯磨き+定期的な歯科医院でのクリーニングが基本です。
✅具体的には、以下のポイントを意識しましょう:
- ・毎日しっかりと歯磨き(とくに歯ぐきとの境目)
- ・フロスや歯間ブラシなどの補助清掃具も併用する
- ・3~6ヶ月に1回は歯科医院でのメンテナンスを受ける
- ・噛み合わせのチェックやインプラント周囲の炎症チェックも定期的に
特に高齢になってからは、ご自身でのケアが難しくなることもあります。
その際は、ご家族や介護者のサポートや、訪問歯科の活用なども検討していきましょう。
歯を失ってしまうことは、見た目や食事の不自由さだけでなく、将来の健康や認知機能にも大きな影響を与えることが分かってきています。
その中で、しっかり噛めることが脳を刺激し、認知症のリスクを下げる可能性があるというのは、とても希望の持てるお話ではないでしょうか。
インプラントは、ただ歯を補うだけの治療ではありません。
「もう一度、自分の歯のように噛めるようになる」という喜びとともに、
食べる楽しみ、会話する楽しみ、生活の自立や心のハリを支える治療です。
そして何より、“今からできる認知症予防”の一歩にもつながる選択肢として、多くの患者様の人生を明るく変えてくれる力があります。
もちろん、治療の可否は年齢や健康状態によって個人差がありますが、
「自分には無理かも」と決めつけてしまう前に、まずはお口の状態を知ることから始めてみませんか?
気になることや不安なことがあれば、どうぞいつでもお気軽にご相談ください。
私たちがお手伝いさせていただきます。
『 東京審美インプラント治療ガイド:監修 松本デンタルオフィス東京 』
監修:松本デンタルオフィス東京
所在地:東京都東大和市清原4丁目10−27 M‐ONEビル 2F
電話:042-569-8127
*監修者
医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス
院長 松本圭史
*経歴
2005年 日本大学歯学部卒業。2005年 日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 入局。
2006年 日本大学歯学部大学院 入学。2010年 同上 卒業。
2010年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 助教
2013年 日本大学歯学部歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座 専修医
2016年 医療法人社団桜風会 松本デンタルオフィス 新規開院
*所属学会
・日本補綴歯科学会
・日本口腔インプラント学会
・日本歯科審美学会
・日本顎咬合学会
*スタディグループ
・5-D Japan
・Esthetic Explores
詳しいプロフィールはこちらより